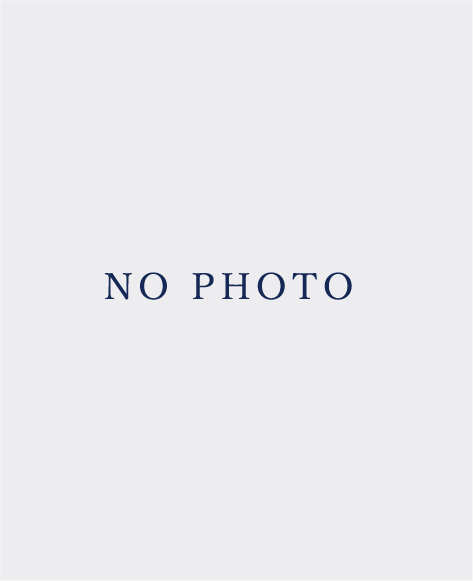税務ガバナンスと外国子会社合算税制における租税負担割合

多国籍企業グループにおいて、親会社が子会社の税務ポジションをモニター、分析し、必要な場合には指導、是正措置をとれる体制を構築することは、税務ガバナンスの観点から有効です。実効税率は、損益計算書の税引き前当期純利益と法人税費用の比率ですが、税法の規定により税法で定められた類似の比率を別途算定することを求められることがあります。具体的には外国子会社合算税制における租税負担割合と国際最低課税額に対する法人税における国別実効税率です。
これらの比率は、会計上の利益あるいは税法上の所得に対する法人所得税の比率であり、算定により得られる情報は類似するものではありますが、外国子会社合算税制における租税負担割合と国際最低課税額に対する法人税における国別実効税率は、それぞれの制度目的に合わせて算式が設計されており、実効税率のように損益計算書から算定可能ではなく、損益計算書に加えて税務申告書からも情報を抽出して算定することが必要です。
目次
外国子会社合算税制における租税負担割合
外国子会社合算税制において、租税負担割合は、特定外国関係会社および対象外国関係会社の会社単位の合算課税、部分対象外国関係会社の特定所得の合算課税を免除する要件となります。すなわち、特定外国関係会社において租税負担割合が27%以上であれば、会社単位の合算課税は免除され(措法66の6⑤一)、対象外国関係会社、部分対象外国関係会社の租税負担割合が20%以上であれば、それぞれ会社単位の合算課税および特定所得の合算課税が免除されます(措法66の6⑤二、措法66の6⑩一)。
租税負担割合は、外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合とされており(措法66の6⑤一括弧書き)、政令(措令39の17の2)では具体的に以下の算式で計算することを規定しています。
租税負担割合の計算式
| ➀+➁+③-④ |
| ⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩-⑪ |
分子
| ➀ | 外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、本店所在地国において課される外国法人税の額 |
| ➁ | 外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額 |
| ③ | 本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるもの(間接外国税額控除の適用がある場合) |
| ④ | 下記⑥に掲げる所得の金額から除かれる本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に対して課される外国法人税の額 |
分母
| ⑤ | 外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税に関する法令により計算した所得の金額 |
| ⑥ | 本店所在地国の法令の規定により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(支払を受ける配当等の額を除く。) |
| ⑦ | 支払う配当等の額で損金の額に算入している金額 |
| ⑧ | 納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額 |
| ⑨ | 積み立てた保険準備金の額のうち損金の額に算入している金額で損金算入限度超過額 |
| ⑩ | 積み立てた保険準備金の取崩し不足による益金算入不足額 |
| ⑪ | 益金に算入した還付を受ける外国法人税の額 |
分子の③「本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるもの」(措令39の17の2②三)は、外国関係会社の所在地国が外国税額控除制度においてかつてわが国が採用していた間接外国税額控除を採用しており、外国税額控除が行われた場合に、控除された外国税額を加算することを意味します。また、④「下記⑥に掲げる所得の金額から除かれる本店所在地国で非課税とされる本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に対して課される外国法人税の額」(措令39の17の2②三イ)は、非課税配当が分母に加算されないことに対応して、非課税配当にかかる源泉税を分子から控除するものです。
非課税所得の意義と範囲
租税負担割合の算定において、分母の⑥「本店所在地国の法令の規定により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(支払を受ける配当等の額を除く。)」(非課税所得)の範囲は明らかにされていません。
措法通66の6-25は、「外国関係会社の本店所在地国へ送金されない限り課税標準に含まれないこととされる国外源泉所得」、「措置法第65条の2の規定に類する制度により決算に基づく所得の金額から控除される特定の取引に係る特別控除額」を例示していますが、やはりその範囲は明らかにされていません。
(出典:国税庁ホームページ「第66条の6~第66条の9 《内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例》関係」)
この点、公益社団法人日本租税研究協会国際課税実務検討会が平成26年6月25日に公表した「外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)における課税上の取扱いについて」には、非課税所得について「外国関係会社の本店所在地国の外国法人税が当該外国関係会社において恒久的に課税されないものが,課税標準に含まれない所得の金額(非課税所得)に該当する。」というコメントがあり、このコメントにもとづけば、課税の繰延措置により課税されない所得は非課税所得に該当しないことになります。この報告書のはしがきには国税庁との協議を踏まえてまとめられたと書かれており、法的な位置付けは明らかではありませんが、実務上の一つのガイダンスになり得るものと考えられます。
(出典:公益社団法人 日本租税研究協会「外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)における課税上の取扱いについて」(平成26年9月))
非課税所得の具体例
措法通66の6-25 の「外国関係会社の本店所在地国へ送金されない限り課税標準に含まれないこととされる国外源泉所得」には、国外所得免除制度を採用している国や地域の国外所得が該当すると考えられます。例えば、香港では、香港の中で行われた経済活動及び香港での貿易取引の収益が課税の対象とされているため、香港子会社の香港域外での経済活動から生ずる収益は非課税所得になると考えられます。(出典:日本貿易振興機構(JETRO)「香港 税制」)また同様に、シンガポールにおいてもシンガポールで生じた所得または稼得された所得(国内源泉所得)、及びシンガポール国外源泉所得のうちシンガポールで受領されたものが課税対象となるため、シンガポール子会社の国外所得でシンガポールに送金されないものは非課税所得になると考えられます。
(出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)シンガポール事務所「シンガポール税制の概要 【2024年改訂版】(2024年9月)」)
また同通達の「決算に基づく所得の金額から控除される特定の取引に係る特別控除額」の例としては、シンガポールにおける企業技術革新スキーム(Enterprise Innovation Scheme)によって適格支出額の 200~400%の損金算入が認められるR&D支出の特別控除等が該当すると思われます。
(出典:ジェトロ「シンガポール税制の概要 【2024年改訂版】」、同上)
また、「外国関係会社において恒久的に課税されないものが,課税標準に含まれない所得の金額に該当する。」という理解にもとづけば、わが国の組織再編税制と同様の外国税制により組織再編成時の資産・負債の帳簿価額の引継ぎにより譲渡損益の課税が繰延べられる場合も非課税所得に該当しないことになります。
連結納税制度やパススルー課税が適用される場合の租税負担割合の計算
会社単位の合算課税の基礎となる適用対象金額を本店所在地国法令に基づき計算する場合、企業集団等所得課税規定を除いた本店所在地国の法令の規定により計算するものとされています(措令39の15➁本文)。租税負担割合の分母、分子の計算においても企業集団等所得課税規定を除いた本店所在地国の法令等の規定により計算するものとされています(措令39の17の2➁一イ括弧書、措令39の17の2➁二括弧書)。
企業集団等所得課税規定とは、連結納税規定とパススルー課税規定からなります。連結納税規定は、外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する一の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国及び本店所在地国以外の国若しくは地域の法令の規定をいいます(措令39の15⑥一、二)。次に、パススルー課税規定は、外国法人の所得を当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱うこととする当該外国法人の本店所在地国の法令の規定をいいます(措令39の15⑥三)。
法令上「企業集団等所得課税規定を除いた本店所在地国の法令の規定により計算する」ことの意味は必ずしも明らかではありませんが、通達により説明がされています。
その説明によれば、連結納税規定が適用される場合には、租税負担割合の算式の分母⑤「外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税に関する法令により計算した所得の金額」は、外国関係会社の属する企業集団の所得ではなく当該外国関係会社の所得に対して法人所得税が課されるものとして、本店所在地国の法令により計算した当該外国関係会社の所得の金額となっています(措法通66の6-24の2、66の6-21の2(1))。
また、分子①「外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、本店所在地国において課される外国法人税の額」及び分子②「外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額」は、連結納税規定を適用しなかった場合に計算された所得の金額について計算した法人所得税の額です(措法通66の6-24の3、66の6-21の5、66の6-21の2(1))。すなわち、外国で連結納税規定を適用して、所得・税額計算を行っていたとしても、外国関係会社個社ベースで租税負担割合を計算する必要があります。
パススルー課税規定が適用される場合には、租税負担割合の算式の分母⑤は、所得のパススルーをした外国関係会社においては、パススルーした所得をその株主等の所得とせず、当該外国関係会社の所得に対して法人所得税が課されるものとして、本店所在地国の法令の規定により計算した当該外国関係会社の所得の金額となり、パススルー課税規定の適用により所得をパススルーされた外国関係会社においては、パススルーされた所得を、当該外国法人の所得として取り扱わないものとして、本店所在地国の法令の規定により計算した当該外国関係会社の所得の金額となります(措法通66の6-24の2、66の6-21の2(2))。
また、パススルー課税規定が適用される場合の分子①は、上記により計算された所得の金額について計算した法人所得税の額です(措法通66の6-24の3、66の6-21の5、66の6-21の2(2))。すなわち、パススルーによる所得の帰属の変更がなかった場合の外国関係会社の所得を計算し、その所得に対応する外国法人税の額を計算して租税負担割合を計算する必要があります。
さらに詳細な事例等について国税庁よりQ&Aが出されています(出典:国税庁ホームページ「連結納税規定等が適用される外国関係会社の適用対象金額等の計算方法等の改正に関するQ&A(情報)」)。
累進税率が適用される場合の租税負担割合の計算
本店所在地国の外国法人税の税率が累進税率によっている場合には、最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額により租税負担割合の計算を計算することができます(措令39の17の2➁四)。
外国関係会社が赤字の場合の租税負担割合の計算
所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率に相当する割合(措令39の17の2➁五)によることとなります。
まとめ
租税負担割合を正しく計算するためには、外国関係会社の財務諸表や税務申告書を入手して、必要な情報を抽出しなければなりません。税務ガバナンスプロセスの一環として海外子会社の財務諸表や税務申告書を入手、保存、レビューすることが望まれます。
東京共同グループの一員であるTKグローバルトランザクションアドバイザリー株式会社では、移転価格税制に対応した各種書類の作成や制度に対する疑問等、グローバルで取引する機会の多い企業に必要なアドバイスやサポートをご提供しており、随時無料相談会を実施しております。これからグローバルで経営を進める予定の企業様や、すでに海外展開していて移転価格税制について不安がある企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。
なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
©2025 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。