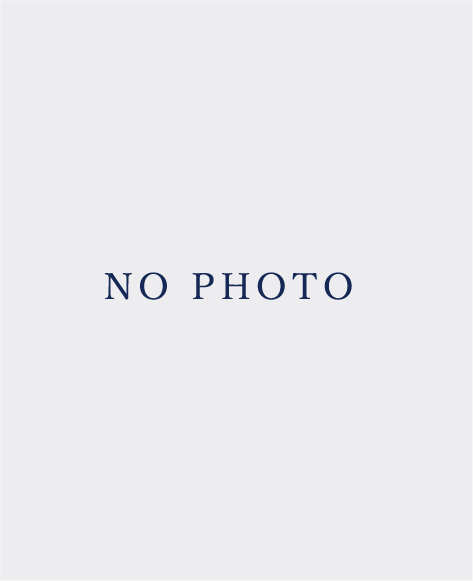同じ物品なのに分類が違う?輸出と輸入で起きる現実と対処法

「同じHSを使っているはずなのに、なぜ輸出国と輸入国で分類が違うのだろう?」と感じたことはありませんか。
EPA特恵関税を活用する実務では、原産地証明と並んでHSの整合性が非常に重要です。ところが、実際の現場では輸出時に適用したHSコード(当該輸出貨物のHS分類番号)が輸入国で認められず、関税優遇を受けられないという事例も聞かれます。
本稿では、HS分類の相違がなぜ起きるのか、その背景にある制度や解釈の違いを掘り下げるとともに、分類トラブルを回避するために実務担当者がとるべき対策について解説します。
目次
HSの分類が一致しないという現実
HSは世界共通の輸出入貨物の分類表なのでは? 実務上起こりうるトラブルとその影響
これまでも述べたとおり、HS(Harmonized System)は、HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)によって定められた商品の分類表です。
HS分類では、加盟国間で輸出入される商品の分類を、HS品目表の規定に従って行うことが定められています。これによって、例えばEPA特恵関税率の適用やその為の原産地の判断において、関係国間の齟齬が生じることを防止しているのです。
HS条約はWCO(世界税関機構)が策定し1988年に発効したもので、2025年7月時点では日本をはじめとして161ヶ国及びEUが加盟しています。そこで使用されるHS品目表は、貿易実務の世界標準として国際的に運用されています。
HSは定期的に改正されるため、どのバージョンを使用しているかについては留意が必要ですが、同じバージョンを使用しているのであれば、同じ物品は同じ項(号)に分類されその番号(HSコードともいう)も同一であるはずです。
(HSの定期的な改正についての詳細はこちらをご参考ください。)
しかし、通関実務の現場では、例えばある商品に関する原産地証明書等が、日本の輸出者と商品の輸出先で「商品のHS分類が誤っている」と輸入国側の税関当局に指摘されるというトラブルが発生するケースがあります。
原産地証明書等は、EPA(経済連携協定)を締結している国家間で約束された低い関税率(特恵関税)を適用するために発行されます。これが認められない場合、輸入者側は関税の負担を減らせず、輸出者側も輸出をしにくくなるなど、双方にとってのメリットを享受できなくなってしまうのです。
分類の相違が起こる理由
言語・文化・解釈の違いがもたらすギャップ
各国間でHS分類に齟齬が起こる原因の一つに、HSの規定の解釈の違いが挙げられます。その要因としては、社会生活様式、習慣、環境、文化の違いがあります。
HS条約は、英語とフランス語の双方が等しく正文とされていますが、起草時、実は、第1類~第49類までは英語でドラフトしたものをフランス語に、第50類〜第97類まではフランス語でドラフトしたものを英語にそれぞれ翻訳しています。
この時点で、英語・フランス語間の翻訳上の微妙な揺らぎが生じる可能性もあり得るでしょう。それに加えて、英語・フランス語圏以外の国では自国語に翻訳する必要があります。
単純に翻訳の揺らぎだけではなく、異なる文化圏では、同一の言葉が同じ商品を示すとは限りません。また、その言葉の意味する範囲も異なる可能性があります。(例えば、日本の梅の果実はあんずやすももなどと同じ項に含まれるか否か等。)
また、言語自体の解釈の問題も発生し得ます。HSには、定義が明確でない、あるいは定めにくいものが存在します。それらを自国語に訳そうとする際、原語国の辞典等も参考に、それに対応する自国語を選ぶのですが、完全に意味が一致する語がみつからない場合、自国の文化的なフィルタをかけて解釈をしてしまう可能性もないとは言えません。
EN(Explanatory Notes)の役割と限界
このような解釈の違いを防止し、HSの適用、分類の統一を図るため、WCOでは、
Explanatory Notes(以下「EN」と略記)を策定し公表しています。
HSには注の規定として、例えば項に記載された物品の定義や、個別具体的に分類のルール等が定められています。しかし、全ての商品をHS品目表として記載することは不可能です。その為、ENによってHS品目表の項の規定の意味やそこに含まれる物品の範囲等を解説する等、可能な限り国によりまた担当者によって解釈に違いが出ないようにしているのです。
日本では、ENをもととし「関税率表解説」(通達)を定めて、関税分類の統一的運用を図っています。(筆者は、HS導入に向けての準備作業の一員として、この翻訳作業にも携わりました。)
例えば、HSにおける第1類「動物(生きているものに限る。)」には、馬、牛、豚、羊等が規定されていますが、ENにはこれらについて詳細な解説がされており、これらの物品に対する正しい理解をサポートするとともに、適切な分類の為に必要な情報が提供されているのです。
ただし、ENにも限界があります。国家間の習慣の違いや、商品の概念にズレがある場合に、ENの解説を踏まえてもなお、分類の相違が起こる可能性もあるのです。
判断が分かれる具体的な事例(いのしし、ライ小麦、ごぼうなど)
HS分類の判断が分かれる具体的な事例をご紹介します。
第1類及び第2類に含まれる項の品名としてswine(豚)が記載されていますが、いのしし(wild boar)は記載がありません。日本では一般的に豚といのししは別の動物と意識していますが、HS品目表上では言語として“wild boar”ということばは使われていません。しかし、ENにはswineには家畜としての豚のほか野生の豚(たとえばいのしし)を含むと記載し、豚と共に同じ項に分類するよう説明しています。
これを受けて日本の関税率表では備考として「第1類から第16類において牛には水牛を含み、豚にはいのししを含む。」と規定しています。(HSの条文ではないのですが日本の関税率表の法律文です。)
また、小麦とライ麦のハイブリッドであるライ小麦の解釈も興味深い事例です。HSでは、小麦は第10.01項に分類され、ライ麦は第 10.02項に分類されています。このライ小麦の分類問題についてはHS委員会で検討の結果、第10.08項のその他の穀物に分類され、その細分として第1008.60号に特掲されることになりました(1992年HS改正)。
更に興味深いのは、ごぼうです。もともと日本のごぼうは、西洋では野菜として食されていなかったため、HS品目表で根菜類として第07.06項に分類されていたものを「その他の植物」に分類変更しました。その結果、関税率が低くなりごぼうの輸入量が急増したのです。現在では「第7類 食用の野菜、根及び塊茎」のうち根菜類の「その他のもの」として第07.06項に分類され直しています。実は、欧州ではサルシファイと呼ばれるごぼうと同種類の根菜が存在します。現在西洋ごぼうとして知られています。
通則や項の規定の解釈による判断のズレ
通則2(a)、3(b)などにおける主観的判断の余地
HS分類に齟齬が起こる2つ目の要因は通則の適用に関するものが挙げられます。通則とは正式には「HSの解釈に関する通則」といい、HS条約の附属書である品目表(これを「HS」といいます。)を構成するHS分類の為のルールです。HSは項及び号の規定並びにこれらの番号、部、類及び号の注の規定並びにこの通則から成っています。ちなみに「HS番号、あるいはHSコード」とはこの項番号(4桁)及び号番号(2桁)を合わせた
6桁の番号のことです。通則は日本においては例えば「関税率表の解釈に関する通則」として関税率表等に定められています。
この通則の規定の適用にあたっても、HS分類の判断にズレが生じる可能性もあるのです。
例えば、通則2(a)には「各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし…」との規定があります。
「未完成」という状態は誰でも判断がつくように思えますが、「完成した物品としての重要な特性を有している」か否かは、判断する人の主観によって異なる可能性があります。
また、例えば2つ以上のHS分類が異なる商品が1つのパッケージとして小売用に包装されている場合、通則3(b)における「小売用のセットにした物品」において「当該物品に重要な特性を与えている構成要素」から成るものとして分類するとされています。
ここも、分類しようとする者によって何が重要な特性を与えているか、判断が分かれる可能性があります。
「さ細な使用」の基準とは?解釈が人によって異なる事例
さらに、貴金属の附属品についても、解釈の余地がありそうです。
HS 第71類(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺模造細貨類並びに貨幣)では「全部又は一部が貴金属又は貴金属を張った金属からなる製品は、……この類の他の注において別段の定めがある場合を除くほか、すべてこの類に属する。」とある一方、同類注2(A)で、「第71.13項から第71.15項までには、貴金属又は貴金属を張った金属をさ細な取付具、装飾物その他の部分(例えば、頭文字、はめ輪及び縁金)のみに使用した物品を含まない。」と規定されています。
この場合の「さ細な取付具、装飾物その他の部分」については、判断する者の解釈が入り込む余地があります。
輸出国と輸入国の分類が違ったときの対応策
正確なHS分類の重要性と「自己責任」の原則
本章では、1つの商品に関し輸出担当者と、輸入国側の税関との間でHS分類が異なっている場合の対応策についてご紹介します。
大前提として、分類の相違を起こさないことが重要です。日本の税関は、「申告された内容は基本的に正しい」という前提で輸出申告書に許可をおこないます。誤っている場合は申告者の自己責任である、ということです。
まずは輸出者側が、商品が何であるかを正確に把握し、慎重に検討したうえでHS分類を行い、該当する項(号)番号を特定することが必要です。
HS分類のポイントとしては、①分類しようとしている商品を正しく把握すること、
②HSの項の規定をEN、関税率表解説等を活用して正しく解釈し適用すること、の2点が挙げられます。
輸入国側の事前教示制度を活用する
例えば、輸出貨物について慎重にHS分類を検討したうえで、「該当する貨物のHS分類の違い」への有効な対応策として挙げられるのが、事前教示制度の活用です。
原産地証明書の作成や発給に先立って、輸出する商品のHS分類について、輸入国の税関に事前に問い合わせ、確認をする制度です。(実際には、輸出先の貨物の輸入者に対して、この制度の利用を依頼する。)
事前教示制度を活用することによって、あらかじめ輸入国の税関と適切なHS分類について擦り合わせが可能となり、安心して原産地証明書を輸入者に提供できます。
また、輸入貨物に対する事前教示とは違い拘束力はありませんが、必要に応じて日本の税関に輸出貨物のHS分類、原産地基準に関する教示を求めておくことも有効です。
なお、念の為ですが、HS分類のタイミングは、それぞれ当該物品の分類判断を行う為に提示された時における、性質・形状等に対して行われるものであることを付記しておきます。
分類判断に必要な情報を輸入者に渡すには?
この事前教示申請の段階においては、輸出者から輸入者に対し、商品の詳細な情報、輸出者側からの分類意見等、HS分類における判断のための最大限の情報を提供するように心がけておきましょう。
なぜなら、輸入貨物について原産地規則に則りEPAの特恵関税を享受するために、輸入国の税関と直接的に対峙するのは輸入者であり、最終判断は輸入国税関当局であるからです。HS分類の根拠や説明ロジックについても提供することで、輸入者による税関当局等に対する理論武装を助けることができるでしょう。
輸入貨物に対する適用関税率、法的手続等は輸入者と税関等その国の関係当局との問題です。
分類の相違が国際問題になるとき
通関紛争が外交案件に発展する流れ
ここまで解説してきたHS分類の相違は、時に国際問題となることがあります。
HS条約第10条第1項では「この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争は、できる限り当該締約国間の交渉によって解決する」と定められています。ただし、第2項では「交渉によつて解決されない紛争は、紛争当事国が統一システム委員会に付託するもの」として、同委員会はその解決のための勧告をおこなう、とも定めています。
具体的に国際問題になるとは、どのようなケースなのでしょうか。
多くの場合は、輸出した商品が輸入国側でのHSの解釈の相違で、結果として高い関税率が適用されるケースです。
このようなケースでは、まずは輸出入に係る事業者から輸入国税関に必要な追加説明をおこない、当該分類の再検討を願い出ることです。しかし、一度発出された税関からの回答を覆すのは難しいケースも多く、輸入国内では、不服申立て、訴訟という手段もあるでしょう。他方、輸出者側としては輸入国側に対して、両国の当局間でのHS分類の相違として、問題提起するということも考えられます。その一つの方法としてHS分類紛争解決手段をとることがあります。
WCO HS委員会での議論と調整プロセス
分類紛争の解決においては、輸出入に係る事業者が在輸入国公館に相談し、そこから2国間の外交ルートを通じての議論となります。
日本からの輸出を例にとると、輸出入に係る事業者は物資所管庁を通して財務省関税局に相談をし、外務省担当部局・その他関係省庁を含めて、相手国の関税当局・その他関係部局と交渉をすることになります。
原則的にHS分類の解釈は、当事国2国間で協議し、解決を図ることになりますが、それでも解決できない場合や、貿易量等が多く国際的影響力も大きい場合などには、WCOのHS委員会に検討を付託し、WCOが解決のための勧告をおこないます。筆者が係ったこうした輸出品に関する事例もあります。
HS委員会は年に2回開催され、各種の物品のHS分類について議論します。同委員会による分類の決定は加盟国による単純投票による多数決によって決定します。その結果を受けてENの改正、分類例規集への収録などHS分類の国際的な統一的運用を図るべく、それぞれ関連部分の修正、勧告がおこなわれます。
過去の実例(日米間でのグルラム問題)
過去の事例としては、HS委員会ではなく二国間で解決した事例として日本に輸入されている集成材の関税分類に対する申立て事件があります。日本では一定の厚さのある木材を重ねて接着した集成材は、第44.12項の積層木材である集成材として分類していました。
一方、ENにおいては第44.18項の建築用木工品には構造用集成材の製品(以下、グルラム)が含まれるとの記述があります。日本の関税率表ではこちらの第44.18項の方が関税率が低く設定されていました。そのため、アメリカは1989年スーパー301条に基づき日本の集成材の関税分類は誤りであり、貿易の不公正慣行であると申立てたのです。(本件は、日・米・当事国間で協議し、一般の集成材と構造用集成材である木製品分類基準を日本から提案し、合意した為制裁には至らず解決した。(筆者が担当した。))
なお、「グルラム」に関しては、2022年のHS改正で第44.18項の細分に構造設計用木材製品としてグルラムが明記されました。単に「グルラム」との名称のみでなく、構造用集成材の製品であるか、単なる積層木材かの区別が重要です。
おわりに:分類の整合性を担保するために
このように、輸出者側、輸入者側、そして輸入国の税関でのHS分類の整合性を担保するためには、輸出者から輸入者への正確で十分な情報の提供とHS分類判断のロジックの提供が大切です。加えて、必要に応じた税関への事前教示制度の活用も重要であるといえます。
特に輸出者においては、原産地証明書を提供する際には、これら情報提供の準備も併せて行い、例えば、EPAの特恵関税措置を輸入者が享受できるよう万全の態勢を整えておくことをおすすめします。
なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
©2025 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。