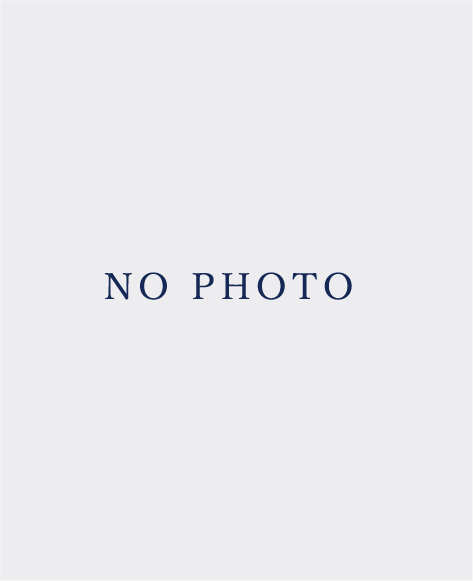HS分類が難しいと言われる理由 ー機械部品と附属品の見極め方

「この部品、HSのどの項及び号コードに分類すればいいんだろう?」
機械類や自動車といった製品のHS分類において、特に迷いやすいのが「部分品」や「附属品」の扱いです。専用部品、共通部品、完成品の一部、後付けの便利品ーー分類の基準は多層的で、判断を難しくする要因が数多くあります。
本稿では、こうした機械類等の部品・附属品の分類が「なぜ分かりにくいのか」という構造的な理由を解説したうえで、実務上どのように整理し、分類作業を進めていけばよいのか、具体例を交えて考察します。
目次
なぜ部分品や附属品の分類は難しいのか
HSでは明確な定義をすることが難しい
部分品や附属品の分類が分かりにくいと感じる理由として、まず挙げられるのは「HSでは、明確な定義をすることが難しい」ことです。HSで部分品の定義が述べられているのは、第15部注2の「汎用性の部分品」のみで、それ以外に具体的な言及はありません。
HS分類では、簡単な部分品ひとつであっても必ずいずれかの項に分類する必要があります。特定の機械の部分品をそれぞれに定義し、全てをその機械の属する項に分類するという方法はとれないのです。
なお、機械類(第16部の第84類及び第85類)の部分品の分類に関するルールは、同部注2から注4までに細かく規定されています。(第87類の自動車等とは異なり、部分品であって附属品ではないことに注意してください。)
つまり担当者は、まず「部分品や附属品がどのような製品の一部を構成するのか」から把握する必要があるのです。
次に挙げられるのは、機械類における「多層構造」の問題です。機械は複数の部分品から構成され、またその部分品も複数の部分品から構成されています。更に、冷蔵庫の部分品でもあり、エアコンの部分品でもある、といった製品が機械類には多く存在するのです。
分類の前に理解しておきたい基本概念
ここでは、HS分類の実践に入る前に理解しておきたい基本概念を説明します。まずは、部分品と附属品の違いです。
部分品は「ある製品を完成させるまでに不可欠なもの」、附属品は「なくてもその機械の機能を果たせるもの」とシンプルに整理できます。
例えば自動車では、エンジン、ピストン、これらを構成するピンやネジまで、自動車としての機能を果たすために必要な全てのものが「部分品」。逆に、カーナビ、オーディオ、フロアマット等の「なくても自動車の機能を果たせるもの」は附属品といえます。
車の購入時は、部分品と附属品は必ずしも分けて提供されるものではありません。多くの場合デーラーから専用のカバー類、タイヤ交換工具一式等のオプション品、サービス品はいずれも車と共に渡されます。しかし、先ほどの考え方の整理に従うと「なくても自動車の機能を果たせるもの」であるため、これらの多くは附属品で少なくとも部分品ではないという扱いになります。ただし、近年、外付けのカーナビではなく、乗用車のインパネに組み込まれているものは、部分品的ではあります。この場合、部分品と判断されたからといって当該カーナビが自動車の部分品の項に分類されるとは限りません。もっとも、第84類の多くの機械類とは異なり、例えば第87.03項の乗用自動車の場合、その専用の部分品も附属品も第87.08項に規定があり同じ項に該当しますが、同項に分類されない部分品・附属品もあります。
分類ルールの読み解き方
関係するHS注の構造を押さえる
次に、HSの構造と分類ルールの読み解き方について解説します。
前にも述べましたが、HS条約は、本文と附属書から成っており、附属書は項又は号の規定、これらの番号、部、類又は号の注の規定及びHSの解釈に関する通則で構成されています。この附属書は品目表であり、単にHS又はHS品目表といいます。
(HSの定期的な改正についての詳細はこちらをご参考ください。)
貿易実務では、担当者はHS品目表を利用し、取り扱い製品がHS品目表内いずれの項(号)に分類されるかを決定します。その分類を決定する際の原則的なルールを定めたものが「HSの解釈に関する通則」(略して「通則」)といいます。また個別の品目の定義やその部又は類の分類に係る具体的な内容等を定めたものが「注」となります。
品目表では、まずは「第1部 動物(生きているものに限る)及び動物性生産品」「第2部 植物性生産品」等、大きなくくりとして「部」にまとめられ、その下の中分類としての類には具体的にその類に含まれる各品目名等の項及び号の規定と該当する4桁の項の番号及び2桁の号番号が定められます。この6桁の番号をHS番号あるいはHSコードと呼んでいます。項番号の最初の2桁は「類」の番号を示しています。先ほどの「注」には「部注」、「類注」、「号注」が定められています。
今回のテーマである「機械類や自動車関連物品の分類」の対象となる部は第16部と第17部です。
第16部は「機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品」とされ、第84類と第85類を含んでいます。
第17部は「車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品」とされ、第86類から第89類までが含まれています。
「専ら又は主として使用される」とは何か
ところで、品目表では「専ら又は主として使用される」という言葉が散見されます。例えば、第84.09項においては「第84.07項又は第84.08項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品」と表記されています。
ここでいう「専ら又は主として使用される」とは、なにを指すのでしょうか。
考えられるのはイメージとしては「専用の部分品」というケースです。これに対して複数の機械に使用される部分品もあるでしょう。
後者の複数の機械類に共通して使用されている物品は「専ら又は主として使用される」と判断することが困難なケースもあります。このような場合も関係する部又は類の「注」の規定に従って分類が可能です。
例えば、前述したとおり機械の部分品については、第16部注の2に詳細に分類のルールが記載されています。うち(c)において「……該当する項がない場合には、第 84.87 項又は第 85.48 項に属する。」と、いずれの項にも属さない機械の部分品について救済措置が記載されているのです。また、二以上の機械を結合した複合機械の分類等については注3、注4の規定があります。
分類の流れと交通整理の技術
通則1による分類と除外規定の使い方
ここからは部分品及び附属品の分類の流れを説明していきます。基本的には、通則に従って以下のステップを通して分類を行います。(この稿では「専ら又は主として使用する」を便宜上「専用の」と記述することとします。)
1.品目表に、特定の機械の専用の部分品あるいは、当該部分品及び附属品自らが該当するとみられる部・類・項があるか目星をつける。あれば当該項の規定を見て、目算が外れていないかを確認する。
2.1. で検討した項及び関係する部・類の注を確認。確認時には特に当該部あるいは類には含まれない物品名等の規定、いわゆる「除外規定」に着目。ここを先に抑えると「検討対象の部分品・附属品が、現在参照している部・類の注のいずれかの項に含まれているかいないか」を明確にできる。
※除外規定とは、部注、類注において「当該部に含まれないもの」、「当該類に含まれないもの」を定めた規定のこと。すなわち、これらの部及び類の注のいずれの項にも含まれないことを定めたも
のです。
3.除外規定に該当しなければ、項を特定する。目星をつけた項だけでなく、該当しそうな項も含めて候補を拾い上げること。
しばしば複数の項が該当しうるケースも存在するため注意。
通則1のみでは決定できない場合
複数の項に該当するとみられる場合は、1つの項に絞らなければなりません。その際これらの項又は注に別段の定め(通則2以下を適用できないと解される規定)がない場合には、通則2以下、特に通則3の規定にも従って物品の所属を決定します。
※部分品及び附属品の検討では、通則1でほとんどの場合決まりますが、場合によっては通則2「未完成品の場合、未組立ての物品、ブランク、他の物質又は材料との混合物又は結合したもの等」通則3「複数の項に該当する場合やセット品となる場合の優先順位」通則4「どの項にも分類できない場合」によることとなる。
分類例① 自動車のエンジン部品
それではここで、乗用自動車のエンジンを例に、前項のステップに準じて分類をしてみましょう。
1.品目表内で該当部分を「部→類→項」の順番で探す。乗用自動車のエンジンの場合は、
a. 第17部 = 「車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品」
b.その中の第87類 = 「鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び
附属品」
c.次に第87類の各項の規定を確認。
d.第87.03項 = 「乗用自動車その他の自動車」
第87.07項 = 「車体(運転室を含むものとし、第87.01項から第87.05項までの
自動車用のものに限る。)」
e.第87.08項 = 「部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車の
ものに限る。)」
f.先ほど、第87.03項の自動車だと確認済なので、この段階ではエンジンは、
第87.08項に定められた「部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動
車用のものに限る。)」に含まれる可能性がある。そのため、第87.08項も候補に
残しておく。
2.次に、関連する注の規定を確認する。
a. 第17部 注2「「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物
品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない」と、除外規定があ
り、当該注(e)に「第 84.01 項から第 84.79 項までの機器及びその部分品」と規
定されている。
b.自動車用のエンジンがこれらの項に該当しないか確認する。
c.第 84.07 項に「ピストン式火花点火内燃機関」が、第 84.08 項に「ピストン式
圧縮点火内燃機関」が掲げられている。
3.HSコードの最終検討を行う。
a. 第87.08項と第84.07項又は第87.08項の候補のうち、87類注2の除外規定に
よって「第87.08項」は否定された。
b.よって、自動車のエンジンはその種類によって第87.07項か第84.08項に分類
されます。
仮に当該注の規定がなく、上記3. で確定できなかった場合は、通則の2~4を参照して、HS上の所属を確定させます。この場合通則3(a)により、最も特殊な限定をして記載している項がこれよりも一般的な記載をしている項に優先するので、結果として、エンジンの種類により同じく第84.07項か又は第84.08項に分類されるでしょう。
分類例② 電動ワイパーモーター
次の例として、自動車用のウインドスクリーンワイパーのモーターを考えてみましょう。
ワイパーのパーツが全て揃って組み立てられていれば、可能性としては自動車用の「部分品及び附属品」であるので第87.08項がまず候補として考えられます。しかし、ワイパーのパーツであるモーター部分のみ単独で提示された場合、「部分品及び附属品」に該当すると言えるでしょうか。
この場合も、分類例①のエンジンと同様「注における除外規定の確認 → 適切な項の検討 → 必要に応じ、可能であれば通則2以下の規定にも従う」という順番で考えます。
除外規定を確認すると、モーターそのものは第17部の注2「(f)電気機器(第85類参照)」に該当することがわかります。よってこの時点で、自動車の部分品である電動ワイパーの中の1パーツのモーターであったとしても、第17部の「車両」のいずれの項にも含まれないと判断できます。
なお、自動車用電動ワイパーそのものについても同注の規定があります。ちなみに「(f)電気機器(第85類参照)」とは、「第85類を参考に見てください」という意味ではなく、「第85類に掲げる電気機器全て」という意味です。第85.12項に「ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)」が明記されており、こちらに該当するので自動車の部分品及び、附属品を定めた第87.08項には分類されません。
分類例③ 車体カバーと荷台シートの違い
応用事例として、難しい問題ですがあえて車を覆うカバーを考えてみます。
乗用車用の車体カバーは、特定の乗用車の大きさ、フェンダーミラーの位置や形に合わせて作られています。よって、専用品ながらも「自動車本体としても、また自動車の機能としても直接関係がないもの」であるため、「乗用車の部分品ではないが附属品」として第87.08項に該当するとの判断もできるかもしれません。
一方、トラックの荷台を覆う荷台シートはどうでしょうか。乗用車と異なり貨物の保護、脱落防止を目的としており、モノにもよりますが他のトラックでも使用したり、別の目的でも使用できたりと、汎用性が高いものです。
このようなトラックの荷台を覆うシートは、第87.08項の「附属品」とは認められなければ、例えば第11部「紡織用繊維及びその製品」も視野に入れて検討することになるでしょう。また、明らかに両面をプラスチックで被覆したものは39類に分類される可能性もあります。
しかしながら、実際にはトラックの荷台を覆うシートでも、そのトラックの荷台の大きさに合わせて、また荷台に設置されたシートの留め具に合わせて固定用の穴が施されているものは、トラックの荷物を風雨等から守るための必需品であるとして、当該トラックの専用の附属品との見方もあります。
ここはいずれもモノの認定の問題です。その上で、HSのどの項に分類するかは次の問題で、項や注の規定で特に除外されていなければ、自動車の部分品及び附属品の項か、またはその材質により紡織用繊維製品か、プラスチックの製品等について検討することになるでしょう。あるいは、除外規定に該当しなければ、後述のように通則3(a)、3(c)の規定によって決定することになるでしょう。乗用自動車用の特定の型式に合わせた防塵カバーの分類も、乗用自動車の附属品として第87.08項に分類することも考えられますが、単にルーズ式のカバーであれば、紡織用繊維製品として第63.07項に分類される可能性があります(第63.07項の解説参照)。
判断が分かれる事例とその落とし穴
専用品でも材料・形状次第で別分類になる例
ここでは、判断が分かれる事例と誤りやすいポイントについて取り上げます。
まずは、製品の専用の部分品です。
機械類の部分品は「専ら又は主として使用する部分品」であっても、必ずしも当該機械が属する項に分類されるとは限りません。
多くの機械類は、複雑であればあるほど、ある部分品が他の機械類にもその構成部品として使われています。該当しそうな項が多くあり、分類判断を迷うケースも珍しくありません。
このような場合は、改めて「当該部分品及び附属品を正確に把握する」という分類の最初のステップに戻って考えることが大切です。
同一製品に対する専用品でも、材料や形状によって別の項に分類されることになったり、全く別の部の項に該当することになったりする可能性があります。
まずは部分品及び附属品を把握し、そのうえで「該当する項に関係する注における除外規定の確認 → 適切な項の検討 → 必要に応じ通則2以降による所属の決定」のプロセスに則って検討するようにしてください。
「附属品」はどこまで含めてよいか
次に「附属品」をどこまで含めてよいか、という判断について解説します。
前記分類例③のように自動車については部分品も附属品も同じ項に含まれますが、附属品かそうでないかの判断が必要になるケースがあります。附属品を含めていいかどうかの線引きは「附属させる製品との関連性」から判断します。
他方、第16部の機械類については「部分品及び附属品」として両者が同じ項に分類されるケースは限られています。(例えば、第84.43項の印刷機、第84.48項に定める紡糸機、織機等の専用の部分品及び附属品等)
当該機械本体の構成部品ではないが、直接的に附属しており簡単に取り外しができないもの、又は、当該機械類に結合してはいないが他の用途には使用できないものであれば、附属品と言える可能性が高くなります。
一方で、特定の機械の附属品として使用すること以外にも用途がある場合は、一般に「専ら又は主として使用される附属品」には該当しないと考えられます。なお、概して機械類はそれぞれが特定の機能を有していることから、附属品というより複合機械(第16部注3の規定)、あるいは個別の構成機器から成る機械(機能ユニット関係)として分類される場合(同部注4)もあるでしょう。
通則3(a)の適用が必要なケース
最後に、部分品及び附属品が2つ以上の項に該当するとみられる場合です。
特定の機械、車などの附属品であると認められたとしても、必ずその「部分品及び附属品」の項に分類されるとは限りません。
このような場合は、他に特段の定めがなければ先ずは通則3(a)の規定を参照します。
複数ある候補の項のうち「最も特殊な限定をして記載している項」を優先させ「より一般的な記載をしている項」を劣後させるのです。
分類しようとしている物品及び該当するとみられる項の規定ぶりによりますが、例えば「部分品及び附属品」という記述よりも「……製の〇〇(製品名)」と具体的に名称が記述されている方が、より限定された規定といえるでしょう。
例えば、乗用自動車の床用のマットで紡織用繊維製のタフトしたじゅうたんで
運転席、助手席、客席用に作られたものは乗用車専用の附属品ですが、同時に第57.02項等の「じゅうたんその他の床用敷物」にも該当します。
この場合、第87.08項「部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車のものに限る)」よりも、例えば第57.02項「じゅうたんその他の床用敷物」の方が特殊な限定をして記載している項といえます。
おわりに:部品・附属品分類に迷わないために
判断を支えるのは「物品の情報」と「項及び注の読み解き」
難しく考えず、ルールに沿って整理することの大切さ
以上のように、機械類等のHS分類は一見すると複雑で、特に「部分品」や「附属品」について判断に迷うケースがしばしば起こります。
しかし実際は、以下2つのポイントを押さえれば他製品と同様、シンプルに判断できます。
1.取り扱う部分品及び附属品を正確に把握すること
2.「注における除外規定の確認 → 適切な項の検討 → 2以上の項に該当するとみられる
場合は別段の規定がなければ通則2以下の規定にも従うこと」の順に丁寧に該当する
項を絞り込むこと
HS分類は、慣れが必要な作業ではありますが、ぜひ粘り強く取り組んでみてください。
なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
©2025 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。