【事例:第1回 レオス・キャピタルワークス株式会社様 】
未上場株投資の新たな道を拓く
―レオス・キャピタルワークスが東京共同会計事務所との共創で生み出したクロスオーバー型投信

公募投資信託を通じて未上場企業に投資する―2024年9月、国内でも数少ない新たな投資信託の仕組みが上場・未上場の壁を越えて始動した。日本の投資環境に新たな潮流をもたらす一大プロジェクトを仕掛けたのは、成長企業を発掘する“目利き力”と、積極的な情報発信を行う、“顔が見える運用”で投資家から支持を集める独立系資産運用会社、レオス・キャピタルワークス株式会社。同社が2024年9月から運用を開始した「ひふみクロスオーバーpro」は、“未上場株投資を民主化”する革新的な投資信託として注目を集めている。未上場企業と個人投資家をつなぐ新しい形の投資信託はどのようにして生み出されたのか。レオス・キャピタルワークスの中路武志氏、堅田雄太氏に話をうかがった。
目次
≪人物紹介≫
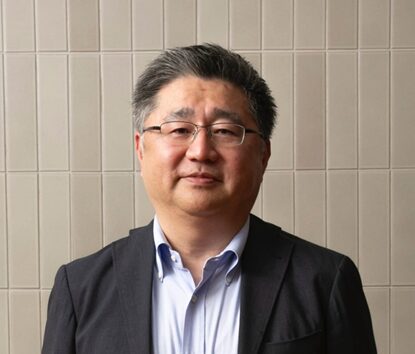
常務取締役 CCO(チーフ・コンプライアンスオフィサー)
コンプライアンス本部長
中路 武志 氏
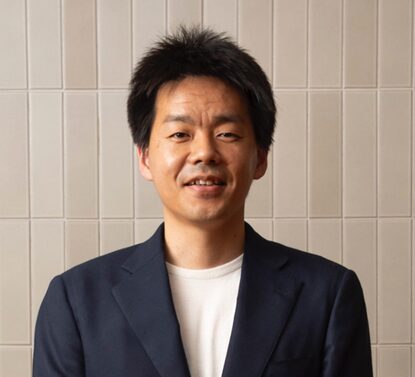
総合企画本部 副本部長 兼 広報IR部長
兼 サステナビリティ経営デザイン室長
堅田 雄太 氏
“未上場株投資の民主化”へ─資本市場に新たな扉を開く
「ひふみクロスオーバーpro」は、上場企業とともに、有望な未上場企業へも投資を行う公募投資信託である。「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに成長企業への投資と向き合い続けてきたレオス・キャピタルワークスならではのビジョンが反映された商品だ。同商品の組成時の営業担当である堅田雄太氏は、商品に込められた思いを次のように語る。
堅田氏:「私たちは創業当時から、お客様にお届けしたい“理想の投資信託”を追い求めてきました。このファンドもまた、当社の代表である藤野が理想としていた商品。ファンドマネージャーとして上場企業への投資に取り組む一方で、未上場企業の成長も支援してきた藤野にとって、未上場企業への投資機会をお客様にも届けることは長年の悲願でした」

―公募投資信託における未上場株の組み入れは、制度上の制約により、実現は困難とされてきた。ところが2022年、政府が「資産運用立国」の構想と実現に向けたアクションプランを打ち出したことで、変化のきっかけが生まれる。ビジョンの中核を成すのは、家計による投資が企業の成長を促し、企業の成長が家計に還元される「成長と分配の好循環」。経済成長をけん引する強固なインベストメントチェーンを創出するべく、官民一体の取り組みが進められるなか、2024年2月に投資信託協会の自主規制ルールが改正され、未上場株の組み入れが可能になった。プロジェクトの中心的役割を担った中路武志氏は、変化の機運を逃さず「ひふみクロスオーバーpro」の立ち上げを推し進めた一人だ。
中路氏:「従来のスタートアップへの投資は億単位のまとまった資金や長期の投資期間が必要で、個人投資家が触れにくい領域でした。しかし、この商品であれば、少額の投資でいつでも解約できる。未上場株の醍醐味にアクセスする機会を広く提供するものです」

―「ひふみクロスオーバーpro」の特徴は、未上場株、上場株の投資を組み合わせるだけではなく、未上場の段階から行う成長企業への投資を、上場後も継続する点にある。「境界を越えて、もっと、ずっとエールを」というキャッチコピーが示すように、未上場と上場の境界を越える“クロスオーバー投資”によって、個人投資家は企業が大きく育つ過程を応援しながらリターンを得ることができる。
堅田氏:「一般的に個人投資家が参加する、いわゆるセカンダリー・マーケットで株を購入しても、その資金は会社に届くわけではなく、マーケットの中でやりとりされるだけです。一方、未上場株への投資では、投資したお金がそのまま企業の成長資金になります」
中路氏:「スタートアップ企業は、人材採用の費用や研究開発の資金など、使途を明確にして出資を受けます。そのため、投資したお金が何に使われているか、投資家が確認しやすい。上場株への投資では得られない“手触り”が、未上場株への投資にはありますね」
堅田氏:「もちろん運用上のメリットもあります。本商品に組み入れるのは投資に見合う水準を満たした、上場間際(レイターステージ)の成長企業。IPO(新規株式公開)に伴う価格上昇や、上場後の成長によるリターンを早期に期待できます。また、マーケットの値動きに影響を受けないため、上場株と合わせて投資してもリスクを分散できるメリットもあります」
―上場後の継続保有によってメリットを得られるのは個人投資家だけではない。資金調達を行うベンチャー企業にとっても、大きな意味を持つ。
中路氏:「スタートアップへの投資は、ベンチャーキャピタル(VC)が主に担ってきました。しかし、日本のVCは創業初期(アーリーステージ)への投資に偏りがちで、IPOを迎えると保有株式を売却してしまいます。そのため、上場直後の企業への支援が途切れ、成長が阻害されてしまう――これは日本のスタートアップを取り巻くエコシステムが抱える、長年の課題でした」
―世界をリードする成長企業を次々と生み出してきた米国では、未上場から上場後も一貫して企業を支えるクロスオーバー投資が定着している。対照的に、日本では上場後の有望な企業を成長させる仕組みが整っていないため、市場をけん引するメガベンチャーが育ちにくい。「ひふみクロスオーバーpro」は、スタートアップを支援する新たなスタンダードとしてクロスオーバー投資を日本に根付かせ、イノベーションの担い手を育てる取り組みでもある。
中路氏:「私たちがさらに大きなファンドになれば、資本政策の工夫によって上場時期を最適なタイミングまで延ばすこともできるでしょう。今後、クロスオーバーファンドが増えれば、より良い形で成長企業を市場に送り出すエコシステムの創出が期待できるんです」
―日本銀行が作成している「資金循環統計(2024年版)」によると日本国内の個人が保有する金融資産は2200兆円を超えると発表しているが、その過半を現預金が占めている。(出典:日本銀行「資金循環統計の解説」)巨額の眠れる資金が成長分野の投資に向かうインパクトの大きさは計り知れない。「ひふみクロスオーバーpro」はスタートアップ投資のあり方、ひいては日本経済を大きく変える可能性を秘めた、資産運用立国の象徴的なモデルケースなのだ。

レオス・キャピタルワークスと東京共同会計事務所が
紡ぐ共創
―しかし、前例のない領域に踏み込み、スキームを一からつくり上げる道のりは平坦ではなかった。
中路氏:「未上場時に投資した株を、上場後も投資信託の枠組みの中で継続して保有する―シンプルな仕組みに見えて、機能させるのは容易ではありません。これまで投資信託で扱うことができなかった未上場株を、投資信託のルールに組み込む。その調整には想像以上の困難がありました」
―「ひふみクロスオーバーpro」は、投資家の資金を集めるベビーファンドと、実際の運用を行うマザーファンドから成るファミリーファンド方式。上場株に投資するファンドと、未上場株・上場株の両方に投資するファンドの2種類のマザーファンドが運用を担う。ポイントは、未上場株への投資を担う主体に投資事業有限責任組合(LPS)を設定している点。LPSは無限責任を負う組合員と、有限責任が担保された組合員で構成されるビークルである。円滑な資金調達を図るために活用されるLPSを、本商品では未上場株の継続保有と、流動性の確保のために活用。企業がIPOを迎えた際にLPSが保有する株式をマザーファンドに現物分配することで、〈未上場→上場→成長〉というライフサイクルを一つのファンドで追い続けるスキームだ。
堅田氏:「ひふみブランドは、できるだけ多くのお客様の資産形成を支えたいという思いを大切にしています。そのため、お客様がいつでも購入・解約できる仕組みを確保することが重要でした」

―未上場株式は市場での売買が難しい。そこで「ひふみクロスオーバーpro」では、親会社のSBIグループがLPS持分を買い取る仕組みを設けることで、未上場株式に投資しながら、ファンド全体として日々の購入・売却を可能にした。しかし、スキームの実現のためには会計面で多くのハードルを乗り越える必要があった。
中路氏:「このスキームは、既存のルールには想定されていないもの。LPSの会計と投資信託の会計という、まったく異なる二つの制度を理解し、うまく融合させるためには、あらゆるイベントをルールに落とし込む必要がありました」
堅田氏:「当初は、自社だけでスキームを構築しようとしました。しかし、課題は想定以上に複雑で、経験豊富な投信計理部門をもってしても対応が難しかった。そのため、専門家の力を借りる方針に切り替えました」
―前例のない挑戦に合流したのが、東京共同会計事務所だ。
中路氏:「かつて私が別のベンチャーキャピタルに在籍していた頃、東京共同会計事務所とともにファンドを組成したことがありました。その当時の経験から、難易度の高い案件を確実にカタチにする、信頼できるスペシャリスト集団だという印象を持っていました」
―白紙からの設計に加え、他社に先駆けてローンチするという目標もあるプロジェクト。厳しい時間の制約がある中で、手探りで正解をつくり上げる試みは容易ではなかったが、レオス・キャピタルワークスの熱意に、東京共同会計事務所も専門家としてのプライドと技術、そして熱意で応えた。
中路氏:「どんなに難しいことでも頑張れば実現する―それが私のモットーです。
ただ、パートナーも同じ覚悟を持ってくれるとは限らない。東京共同会計事務所は、私たちが求めるスピード感に応え、あらゆるサポートを即座に提供してくれました。もしも支援がなければ、プロジェクトはペースダウンせざるを得なかったかもしれません」

制度改正によって道は示されたが、その先の道は自分たちで作らなければならない。
ローンチが急がれる一方で、会計処理における課題は山積みだった。
中路氏:「たとえば、未公開株の時価を日次でどう算出するか。また、IPOやロックアップ期間中に株価が急騰した場合にどうするか。未上場株の組み入れ比率は、全体で15%以下、同一銘柄で10%以下に保つ必要があります。比率が大幅に変わってしまうケースはごく稀ではあるものの、前例がない本商品では、あらゆるケースの想定が必要でした」
―従来型のLPSは、四半期決算ごとの時価評価が一般的である。しかし、いつでも解約できる投資信託では、日々の基準価額を算出するために、時価評価を日次で行う必要がある。さらに商品の骨格を成すLPSによる現物分配も、制度上は存在するものの実務で使われた例がほとんどないルールに依拠する。ユースケースの少ない仕組みを、投資信託の会計ルールにどう組み込むか。想定されるイベントの洗い出しから始まり、組み入れ比率の保持にも対応できるLPSの会計処理や投資信託の計理処理の案出、システムのフィジビリティ検証、関係機関との手続きに至るまで、東京共同会計事務所は緻密にフローを組み立てていった。
堅田氏:「プロジェクトを進める中で、中路は常に『きちっとしよう』と強くこだわっていました。先陣を切るからこそ王道を貫き、他社に追随されても恥ずかしくない仕組みに仕上げようと。その分、難易度は高まりましたが、未上場株と上場株、いずれの投資にもノウハウを持つ私たちが取り組む意義はあったと感じています」
―ミーティングは週次で開催された。推進力となったのは、東京共同会計事務所の専門知と、投資信託におけるレオス・キャピタルワークスの豊富なノウハウ。さらに関係各所への調整をスムーズに進めるため大手会計事務所の協力も得ながら、組織の垣根を越えて一気通貫で仕組みづくりを進めた。そして2024年9月、共創が実を結び、制度改正からわずか半年ほどでのローンチが実現した。
中路氏:「私はルールがないところにルールをつくるのが楽しいタイプ。しかし、詳細なルールを作るとなると、やはり専門家の知見は欠かせません。東京共同会計事務所の協力がなければ成立しなかったプロジェクトでした」
スタートアップ支援の新地図─ひふみクロスオーバーproが拓く未来
―商品の提供開始から半年足らずで純資産残高は約3倍に拡大。販売パートナーも順調に増え、“未上場株に投資できる投信”という新たな選択肢に対する市場の期待が着実に高まっている。
中路氏:「スタートアップ界隈では、ベンチャーキャピタルとは異なる立ち位置のファンドとして見てもらえているようです。投資枠が埋まりがちな人気銘柄でも、本ファンドには特別枠を用意していただくこともあります。想定以上に、上場後も支援を続けてほしいというスタートアップ側のニーズは強いと実感しています」
―クロスオーバー投資が日本に広がれば、スタートアップの“その後”も見据えた資本の流れが生まれる。スタートアップが次のステージへと成長するための土壌が、少しずつ豊かになりつつある。
中路氏:「最終的には、このファンドをIPO直前のラウンドをリードできる規模にまで成長させたいと考えています。そして他社の参入を促し、クロスオーバー投資の浸透につなげていきたい。スタートアップから大型株へ、企業の成長に長期で伴走できる仕組みを、日本に根づかせたいですね」
―企業の成長と個人の資産形成の相互作用を促す官民一体の潮流の中で、スタートアップの成長ステージ全体をカバーする“新しい金融インフラ”を提示した「ひふみクロスオーバーpro」。レオス・キャピタルワークスと東京共同会計事務所が手を携えた“共創モデル”は、次のステージへと歩みを進めている。
堅田氏:「本商品は制度改正から間もなく生まれたもの。ルールの追加やさらなる改正が予想されますが、都度、お客様にとってよりよい資産運用の選択肢を検討していきたい。柔軟に伴走してくれる存在は今後も欠かせません」
中路氏:「誰も手をつけていない新しい金融スキームを広めていくには、挑戦を続ける覚悟が必要です。挑戦には不安も伴いますが、東京共同会計事務所のようなパートナーがいてくれれば心強い。これからも共に新たな領域を切り拓いていきたいですね」

次回は東京共同会計事務所の本プロジェクトにおける支援内容の詳細を、担当者の目線でスキームやコミュニケーションをポイントに解説しています。
▶第2回:“未上場株投資の民主化”を確かな設計力と専門知識で実装 飽くなき挑戦で日本の金融イノベーションを支える
なお、本インタビュー記事は当事務所での取り扱い案件のご紹介を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でお願いいたします。また、個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
©2025 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。


